U-PARL特任研究員 宮本亮一
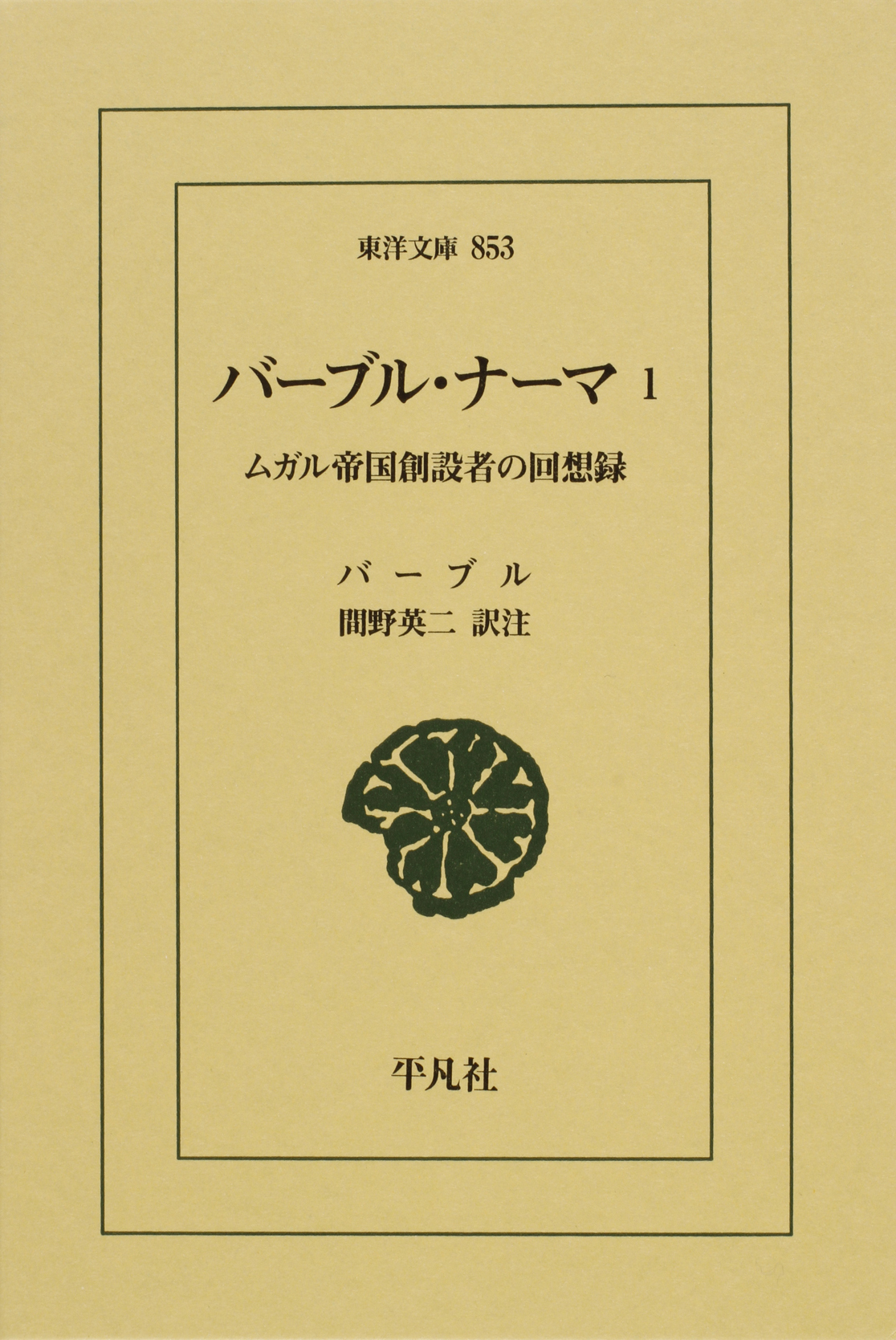 |
 |
 |
今回のコラムでは,ティムール朝の王子として生まれ,ムガル帝国の創始者となった,ザヒールッ・ディーン・ムハンマド・バーブル(1483〜1530年)が,彼の母語チャガタイ・テュルク語(*1)で書き残した回顧録,通称『バーブル・ナーマ(*2)』の日本語訳注を紹介したいと思います。
この書籍は3冊本なのでコラムのシリーズ名(「アジア研究この一冊!」)と齟齬をきたしている,という指摘はひとまず措くとしても,その価値を良く知る人たちは,今頃になって改めて本書を取り上げる必要がどこにあるのか,とさぞ不審に思われることでしょう。実際,本書,そしてその元になった研究書(間野英二『バーブル・ナーマの研究』I-IV,松香堂,1995-2001年)の書評や紹介文は多数発表されていて,これらを読めば,本書がアジア研究においてどれほど重要な価値を持っているのか,容易に知ることができます(*3)。
ではなぜここで本書を取り上げるのでしょうか。それは,これまでに書かれた文章が,本書の魅力を十分に伝えているものの,例外なくイスラーム時代を専門とする研究者によって書かれたものだからです。私は常々,本書の価値や重要性を考えると,この時代に詳しくない,あるいはもっと古い時代に関心がある人に向けての読書案内があっても良いと考えていました。そこで,本コラムでは,前イスラーム時代の中央ユーラシア史を研究する私が,これまでとは異なる視点から本書を紹介してみたいと思います。
本書は,『バーブル・ナーマの研究』III訳注(松香堂,1998年)から改訂された訳文に,解題,術語解説,略年譜,訳注者自身の研究回顧録などを加えたものとなっています。訳文はバーブルの人生に沿って3部に分けられ,それぞれに,彼が活動した3つの地方,フェルガーナ,カーブル,ヒンドゥスターンの名前がつけられています(*4)。バーブルは各地域の特徴をとても細かく描写しており,その記述対象は,気候,地勢,動植物,言語,都市の様子,特産物など多岐に渡っています。イスラーム時代の中央ユーラシア史を良く知らない,あるいは全く知らない人でも,この部分を読むだけで,とても楽しい読書体験が得られるでしょう(*5)。
例えば,バードウォッチングが趣味の私は,本書に時折現れる野鳥の記述を興味津々で読みました。調べていないので確かなことは言えませんが,本書に登場する野鳥で日本まで渡るものはいないかもしれません。それでも,例え日本で観察できないとしても,野鳥が好きな人なら,こうした記述を読むだけで,知的好奇心が大いに刺激されるのではないでしょうか。
話を元に戻すと,バーブルが,自身と関係する人々について記した評伝が含まれていることも,本書の大きな特徴の1つで,その内容は,経歴,系譜,容姿,性格,家族構成などとても幅広いものです。評伝に限らず,バーブルの言葉はとても率直で,それは時に読む者を楽しませ,時に読む者の心を打ちます。
例えば,叔父たちに向けた,「性格ではけちくささがまさっていた(1巻59ページ)」とか,「あのような詩であれば,作るより作らぬ方がましであった(1巻74ページ)」という評価には,思わず笑みをこぼしてしまいます。一方,母の死去に対する,「慟哭がまた新たとなり,別離の悲しみは無限であった(2巻101ページ)」という表現や,長男に宛てた書簡の,「お前に会いたいとお前のことを思いながら,挨拶の言葉を送ります(3巻242ページ)」という一文などは,シンプルがゆえに印象深く,バーブルの家族を想う強い気持ちが伝わります。
さて,本書を読み始めるとすぐに,多くの読者が同じ疑問を抱くのではないでしょうか。「この文章は本当にもともと外国語で書かれたものなのか?」と。それほどまでに訳者の日本語は平明で美しく,読み易いものです。和訳がスムーズに頭に入らず読むのを止めてしまった翻訳作品があるのは私だけではないと思いますが,本書にそのような心配は全くありません。
ところで,前イスラーム時代の中央ユーラシア史を研究する人間は,貴重な現地情報として,玄奘(602〜664年)の旅行記『大唐西域記』(*6)を頻繁に利用しますが,実は,この仏僧の記録とバーブルの文章との間には興味深い一致が見られます。それはインドの境界に対する認識です。
このコラムを読まれている方々の中には,インドという地名を聞いたことがない人はいないはずですし,その場所を思い浮かべられない人も少ないに違いありません。ところが,中央ユーラシアから陸路で向かう場合,どこまで来ればインドなのか,はっきり答えられる人はそう多くないでしょう。もちろん,玄奘はこの問いの答えを残しています。そして,バーブルの記述は,その答えをさらに確実なものにしてくれます。彼が最初のインド遠征に向かった際の記述を引用してみましょう。
「(910年)シャーバーン月(1505年1/2月),太陽が宝瓶宮にあった時,私はカーブルからヒンドゥスターンめざして出馬した。(…中略…)私はそれまでに温暖地帯の諸地方やヒンドゥスターン一帯を見たことがなかった。ニーグナハールに到着するや否や,眼前に別世界が広がった。草も木も獣も鳥も異なっていた。人々の習慣・風習も異なっていた。私たちは驚嘆した。まことに驚異の世界であった。」(2巻76ページ)
インド世界へ足を踏み入れたバーブルが,自身を取り巻く環境の変化にどれほど衝撃を受けたか,この一節を読めば立ち所に理解できるでしょう。ここで強調したいのは,彼がニーグナハール(現ナンガルハール)へ到着した時にその変化を認めたことです。一方,玄奘はヒンドゥークシュ山脈を越え,梵衍那(バーミヤーン),迦畢試(カーピシー)とたどり,次の濫波国(現ラグマーン)に到着したところで,そこがインドの北の境界だと言っています。ナンガルハールとラグマーンは東西に隣接する地域なので,大きく時代を隔てた2人の認識はほとんど一致しています。つまり私たちは,彼らの証言から,一部とはいえ,インド世界の境界をかなり正確に知ることができるのです。
本書には,前イスラーム時代の歴史を考える際に参考となる貴重な情報が他にもあります。例えば,地震に関する記述がそうです。バーブルによると,1505年,カーブルで発生した大地震によって大きな被害が生じ(2巻101-103ページ),1519年にはバジャウルでも地震が発生しました(2巻259ページ)。そして,バーブルのおよそ1300年前にも,西北インドで巨大な地震が発生していました。仏教彫刻で有名なガンダーラでは,寺院などの建造物が大きく損壊した一方,復興の過程で新たな彫刻の製造技術が生まれ,素材選びに変化が生じたことが明らかになっていますが,当時の状況を正確に知ることが難しい考古学者は,地震やその被害の規模を考える一助として,バーブルの記述を利用しているのです(*7)。
バーブルが行った犀狩りも重要です(2巻272-273ページ,3巻21-23,76-78,283ページ)。21世紀に入り,アフガニスタン北東部のプリ・フムリー近郊で,サーサーン朝のシャープール1世(治239-270年)らしき王が犀を狩っている場面を表した巨大な浮彫が発見されました(*8)。研究者たちは,実際にそうであったかどうかは別として,王の支配がインド世界に及んでいたことを主張するために犀(インドサイ)を狩るシーンが描かれたと考えていますが,ここでも,インドで犀狩りを行った歴史上の人物としてバーブルが取り上げられ,その記述が参照されています。ちなみにこの浮彫には,インド世界の象徴として,王と2頭の犀の間にマンゴーの樹も描かれています。この魅惑的な「果実の王様」については,須永特任研究員が執筆されているこちらのコラムを是非ご覧下さい。
ここまで,自分の専門に引きつける形で本書の一部を簡単に紹介してきましたが,最後に私的な文章を付け加えることをお許し頂きたいと思います。大学院進学後,私は本書の訳注者である間野英二先生の指導を受ける機会に恵まれました。これは,私の人生最大の幸運と言えるものです。先生からは,歴史研究を行う上で重要な多くの事柄を学びましたが,その中で,チャガタイ・テュルク語をはじめとするいくつかのテュルク系言語もご教授頂きました。現在,私が研究でテュルク系言語の資料を利用することはほとんどありませんが,それでも,私にとって本書は,開くたびに,先生の教えや,楽しかった(ただし予習は大変だった)講義を思い出すことができる,とても大切なものです。もし,この小文を通じて,本書をまだ読まれていない方の興味が掻き立てられ,その読者が1人でも増えるとすれば,それは私にとって大きな喜びです。中央ユーラシアの歴史を研究する人間が,時代を超えて本書を利用し続けることは間違いありませんが,広く歴史に関心を持つ一般の方々にも,ぜひ本書を手に取り,バーブルの残した魅力的な文章を味わって頂きたいと思います。
【注】
*1 チャガタイ・テュルク語は,ティムール朝時代を中心に広く中央アジアで用いられたテュルク語ですが,ペルシア語とアラビア語の語彙も多量に含んでいます。例えば,「フェルガーナ地方は第5気候帯に属する(Ferghāna vilāyatı beshinchi iqlīmdin dur)」という文章では,Ferghānaはペルシア語,vilāyat「地方」とiqlīm「気候帯」はアラビア語(ただし,後者はギリシア語からの借用語),そして,vilāyatとiqlīmに付された接尾辞の–ıと–din,序数のbeshinchi「第5」,動詞のdurがテュルク語です。
*2 原題はVaqāyi‘といい,ペルシア語に入ったアラビア語wāqi‘a「出来事」の複数形です。
*3 本書の紹介文は,『史学雑誌』124/8, 2015年に掲載されています。また,『バーブル・ナーマの研究』I-IVの書評・紹介は,『西南アジア研究』45, 1996年;『東洋史研究』56/1, 1997年;『史学雑誌』108/2, 1999年;『史林』82/6, 1999年;『東洋史研究』61/4, 2003年に掲載されています。特に,濱田正美によって書かれた書評(『東洋史研究』61/4)の冒頭(729ページ)に見える,「全四巻二五〇〇ページを超える大著は,東洋学の一分野としての中央アジア研究が二〇世紀の末に到達した地点に建てられた金字塔であり,かりそめにもこの分野の研究自体が廃絶することのない限り,将来のあらゆる研究が依るべき不動の基盤である」という一文は,本書を含む一連の研究の価値を表現する,最も的確で最も美しい文章と言えるでしょう。
*4 バーブルの人生を詳しく知りたい方には,まずは,本書の訳注者によって一般向けに書かれた伝記をお勧めします(間野英二『バーブル:ムガル帝国の創設者』世界史リブレット人46,山川出版社,2013年)。
*5 フェルガーナについては1巻17–27ページに,カーブルについては2巻35–73ページに,ヒンドゥスターンについては3巻63–116ページに詳しい解説があります。
*6 現在利用しやすい『大唐西域記』は,水谷真成,あるいは桑山正進による翻訳です。前者は全訳で,言語学的な注釈が豊富です。一方後者は,ヒンドゥークシュ山脈南北と西北インドの部分に特化した抄訳ですが,極めて重要な歴史学的注釈が付されています。
*7 内記理『ガンダーラ彫刻と仏教』京都大学学術出版会, 2016年, 203-235ページ。
*8 Grenet, F. “Découverte d’un relief sassanide dans le Nord de l’Afghanistan”, Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 149/1, pp. 115-134, 2005; Grenet, F., J. Lee, P. Martinez & F. Ory “The Sasanian Relief at Rag-i Bibi (Northern Afghanistan)”, in: Cribb, J. & G. Herrmann (eds.) After Alexander: Central Asia before Islam, Oxford, pp. 243-267, 2007.
【書誌情報】
著者・訳注者:バーブル(著)・間野英二(訳注)
シリーズ名:東洋文庫(853, 855, 857)
出版地・出版社:東京・平凡社
出版年:2014-2015年
ISBN:9784582808537; 9784582808551; 9784582808575
https://www.heibonsha.co.jp/book/b182289.html
https://www.heibonsha.co.jp/book/b185019.html
https://www.heibonsha.co.jp/book/b190654.html
http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_link/bibid/2003213834
2021.10.5

